ライフウェルでは、重症心身障がい児へのケアに力を入れています。看護師、作業療法士、理学療法士、保育士と、専門的なスキルを持った職員が所属しており、お子さんへの医療的なケアはもちろん、自分らしい生活を送るための支援を行なっています。
重症心身障がい児へのケアというのは、具体的にどのようなことを行なっているのかあまり知られていない部分も多く、ケアを実施している施設を見つけることができない保護者の方などもいらっしゃいます。
今回は、ライフウェル・新屋敷事業所の施設長及び、放課後等デイサービスの児童発達管理責任者である東さんへインタビューを行いました。
東さんは、総合病院や看護学校の教員などの経験を経て、現在、療育現場の看護師として働いていらっしゃいます。あらゆる視点から、重症心身障がい児へのケアについてお話しいただきました。
——看護師としての仕事内容について教えてください。

ライフウェルは重症心身障がい児さん対応の療育施設です。子どもさんの成長・発達のために、今どんな支援が必要かを考え、子どもさん一人一人に必要な支援を提供する福祉事業所になります。
医療(病院など)は治療の場ですが、当事業所は福祉事業所なので“生活の質を上げる”、“生活の質をもっと豊かに”といった位置付けの施設になると思います。
私は看護師ですが、作業療法士や理学療法士、保育士などあらゆる職種の職員がいて、全員が療育者という立場で子どもさんたちにかかわっていきます。各職種がそれぞれの強みを生かしながら連携しつつ、お子さん一人一人の状態を正しく評価し、子どもさんのことを理解したうえで関わっていきます。
医療的ケアについても少し詳しくお話しします。例えば日々の生活の中で、胃のチューブから栄養を注入しなければならない、痰がとても多くて吸引をしなければいけない、管を入れておしっこを出さなければいけない、など様々な医療的ケアが必要なお子さんがおられるんですね。
事業所では、ご自宅で実施されている医療的なケアを、私たち看護師で対応させていただく事になります。まずはご自宅でどのような様子で過ごされているかなどお話を伺い、ご家族と一緒に実際ケアをさせていただき、子どもさんの状態を分かったうえで対応させていただきます。経験豊富な看護師が在籍していますので、自宅でのケアについて悩まれていることなどあればご相談に乗ることもできますし、一緒に良い方法を考えることもできると思います。
事業所での看護師の役割は、療育者であることはもちろんですが、お子さんの身体状況や心の状態などを正しく把握したうえで、遊んだり活動したりできる状態かどうかをしっかり判断し、みんなと一緒に楽しく活動できる空間を作る縁の下の力持ちになることだと思っています。
私たち看護師が、子どもさんの体調面を把握し管理できていれば、呼吸器をつけていてもトランポリンで楽しんだり、ボールプールに入ったり、お散歩に行ったりなど安心・安全に活動することができるんですよ。
——重症心身障がい児に対する専門的なケア内容や、ケアの目的や特色などを質問させていただければと思います。

まずは、主治医の先生から、お子さんにはこういう医療的ケアが必要ですという「意見書」をいただきます。次にいただいた意見書に沿う形で保護者さんからこういうことをしてくださいという「依頼書」をいただきます。
それらを拝見した上で、私たちが医療的ケアの看護計画書を立て、保護者の方にも確認していただきます。
最初はお家でどうされているかというのをまずお伝えいただいて、体調管理などのケアの方針について情報収集を行います。
お子さんごとに個別支援計画という計画書を立てるのですが、医療的ケアが必要でないお子さんもいらっしゃいますし、一方で呼吸器を装着して生活している子どもさんもいて、重症心身障がいのお子さんといっても、一人ひとり必要なケアは異なるのです。
例えば、栄養の注入一つをとっても、少し間隔をおいてゆっくり注射器で注入を行うというお子さんもいれば、イリゲーターという器具を使って、点滴のように滴下でお腹に入れないといけないというお子さんもいますし、本当にお子さんによってケアの内容は細かく変わってきますね。
また、医療的ケアが必要なお子さんでも、お友だちと一緒に遊べるよう工夫するのも私たちの仕事です。
目に見える反応は大きなものでなくても、様々な良い刺激を受けることで笑顔を見せてくれるお子さんもいますし、沢山の経験ができるということは成長発達を促すことにもつながってくるので、とにかくできることを目一杯させてあげようという気持ちでいます。
子どもさんの経験値が限られていると興味の選択肢も限られてきますが、経験値が増えていくことで、遊びたいものや好きなものの選択肢が増え「自分で選べる」ようになってきます。まずは多くの経験を積むことでいろんな楽しいことや嬉しいこと、びっくりすることなど多くのことを知ってほしいなと思っています。
ライフウェルのような療育施設に通っていただくことで生活の質、遊びの質、安心を担保した上で様々な体験ができ、自分らしい生活につながっていくのかなと思います。
——看護師のお仕事で大切にしていることや心がけていることを教えてください。

お子さんのちょっとしたサインも見逃さず、気付けるような自分でいたいです。
表情の変化が少ないように見える子どもさんでも、実は視線やちょっとした指の動きで意思表示をしてくれていたり、子どもさんによっては心臓の脈拍(ドキドキ)が早くなるなど、いろいろなサインを出してくれているんです。
こちらの気持ちは必ず子どもさんに伝わっていると思いますし、感じ取る力のある子どもさん達だと思っています。体調面もそうですけど、子どもさんからの発信を見逃さないような自分でいる事を心掛けています。
お子さんと関わっていくと、「あっ!笑っているのね」ってわかる時があるんですね。その子との信頼関係だったり、あとは経験の積み重ねでしょうか。どのような思いで関わるか、それが気づきにもつながっていくのかなと思います。
——これまでの仕事で印象的だったエピソードを教えてください。

私は長年、病院で医療に携わってきたのですが、療育の現場にきたときに「あっ!お子さんとこんな風に遊べるんだ!」という気づきがありました。
ライフウェルには季節の行事がありまして、1月になったら書き初めをするんですね。
お子さんと一緒に書き初めをするときに、サインを出せる子に何を書きたいか聞いてみたんです。「ひらがなと漢字どっちで書きたい?」って聞いたら漢字がいいって答えてくれて。ただそこから、なかなか書きたい漢字が見つからない。
10分ぐらいやりとりをしていたのですが、ふと「夢」はどう?って聞いたらものすごく良い反応を見せてくれたんですよ。どうやら「夢」と書きたかったみたいで。
その時に、お子さんたちはあれを書きたい、あれをやりたいと、きちんと思っているんだなと感じたんです。だからそのお子さんも、諦めずに一所懸命、返事をしてくれていたのだと思うのですが、最後にそれそれ!と意思疎通できた時に、もう本当に嬉しくて。
その出来事が今でも印象に残ってます。夢を書きたいというお子さんの“夢”が実現するように関わっていきたいと感じました。
——重症心身障がい児をケアする看護師として働くために、必要なスキルはありますか?
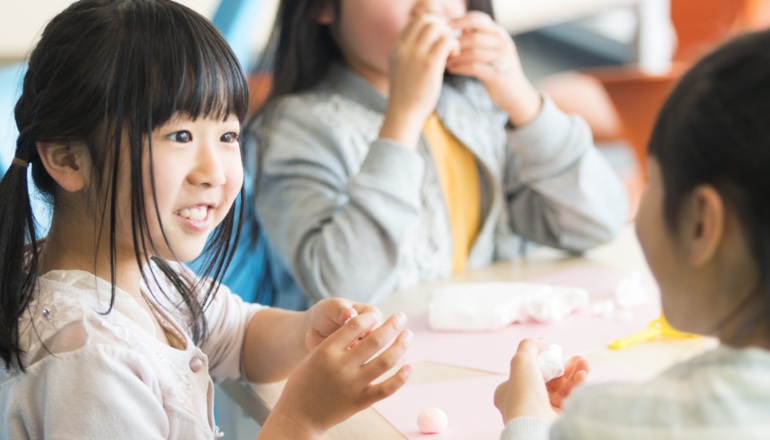
まずは正しく観察ができること。お子さんの身体のことや体調のこと、観察した情報から正しく子どものアセスメント(評価)ができることでしょうか。
この状態は今、慌てないといけないことなのか、それとも様子をみてもいいことなのか、普段と違うちょっとした変化に気づけるような観察ができるか。
いろいろ体調のことを総合的に判断して、これなら大丈夫という判断できる能力が必要だと思います。
医師が近くにいませんし、看護師がその役割を担うことになるので、もし救急搬送しないといけないという状況なのであれば、迅速に判断して救急車を呼ばないといけませんから。
あとは、やっぱりお子さんに興味を持って、しっかりコミュニケーションを図ることができるということでしょうか。
興味を持っていれば身体のことも知りたくなるし、お子さんと一緒に楽しく遊びたいと思えるとともに、向上心にもつながっていくと思います。
実際に私も、お子さん一人ひとりのことを知ろうという姿勢でずっとやってきましたし、一番大切な要素だと思っています。
——最後に、小児分野で働くことに興味がある方へメッセージをお願いします。
先ほどと同じになりますが、お子さんの成長・発達に携われる仕事で、とてもやりがいがあります。
小さな頃から高校卒業まで携わるお子さんもいるんですけど、皆さん目を見張るような成長をしていかれます。その成長に携われるのは、やりがいがあるばかりでなく、自分自身の学びや成長にもつながっていくので、ぜひ一度興味を持っていただけたら嬉しいです。
小児の経験がない方もいらっしゃると思うんですが、看護の基礎技術や、きちんと聴診できる、観察する力があるなど、病院などで基本的に使う看護技術が身についておられれば、教えてくれる先輩看護師もたくさんいますし、一緒に学んでいくこともできます。
あとはやる気ですね。やるぞ!という気持ちできていただけたらと思います。
子どもの笑顔は宝ですからね。

コメント